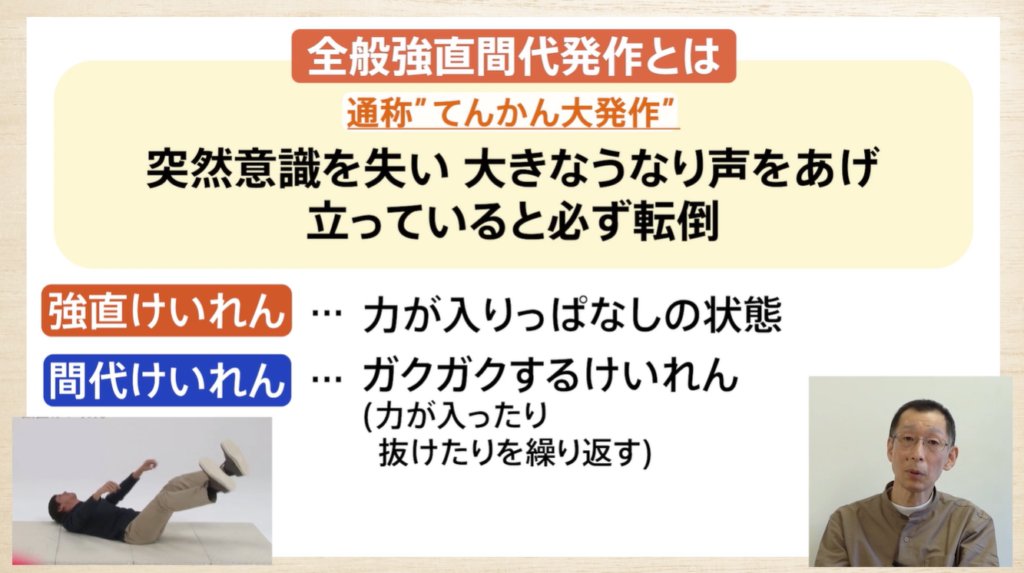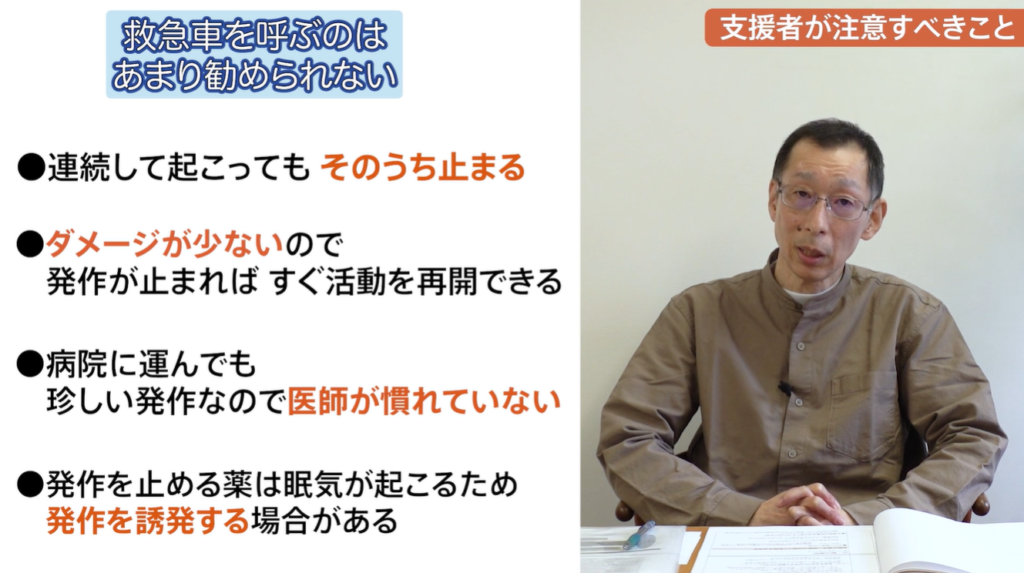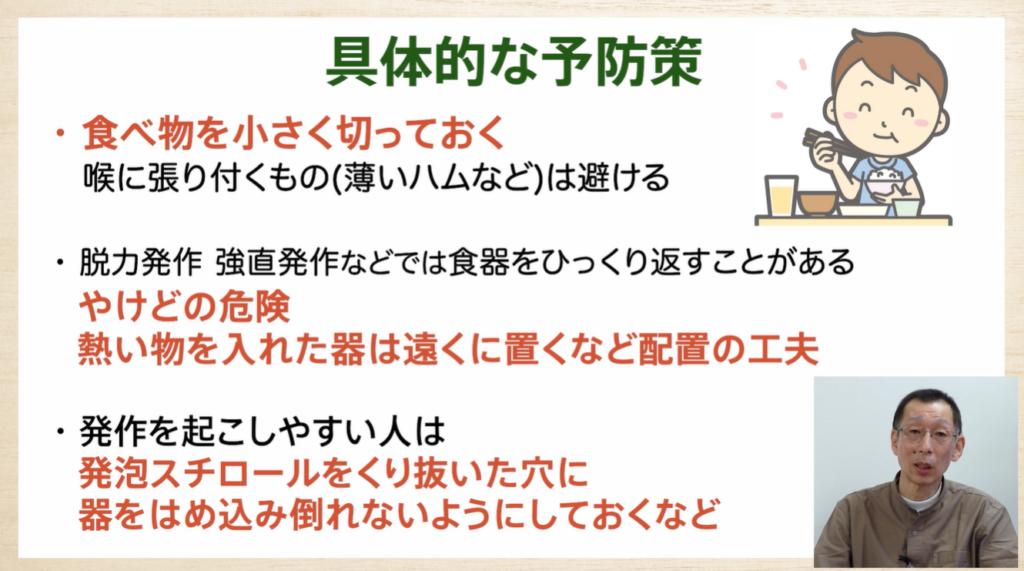就労継続支援B型事業所・ショートステイを活用した自立生活への第一歩
インクルTech※(インクルテック)で社会課題を解決する「株式会社Lean on Me」(リーンオンミー、本社:大阪府高槻市、代表取締役:志村駿介)は、障がい福祉に関わる方を対象に提供する障がい福祉専用eラーニング「Special Learning(スペシャルラーニング)」に、新たな研修コンテンツをアップしました。
※インクルTechとは、インクルージョン(Inclusion)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語で、SDGsに関心が高まる今、ソーシャルな課題の中でも、多様性の包摂を実現するテクノロジーを意味しております。
今回アップしたのは、「ダウン症のある青年の1日密着」と題するコンテンツ。
本編は「作業所編」と「ショートステイ編」の2部構成になっています。
「作業所編」では日中の就労継続支援B型事業所で活動される様子を、「ショートステイ編」では短期入所施設で過ごされる様子をご紹介します。

ダウン症のある方や、障がいのある方が、
特別支援学校を卒業後どのような生活をされているのか?
その先の「親なきあと」を見据えて、準備されていることがあるのか? など、
「少し先の将来イメージを持っておきたい」という
親御さんの不安や想いのヒントになる動画コンテンツとなっています。
自立した生活の一歩として、自身の希望にそって進路選択された青年のリアルな一日。
ご本人の様子や、親御さん、また各事業所・施設の運営スタッフからのメッセージを通じて、障がいのある方の支援に携わるすべての方に、青年期以降の将来を見据えた支援の在り方や、ご本人と関わる上で大切なことなどを考える一助になればと思います。
■撮影ご協力
・就労継続支援B型事業所 「スマイルジョブくずは」
・特定非営利活動法人たゆらぎ 「ショートステイ みっきぃ」
■具体的なコンテンツ紹介
◇「ダウン症のある青年の1日密着~作業所編~」

一般就労に必要なスキルを身につけるための就労訓練の場である就労継続支援B型事業所では、本人の得意・不得意や個性を尊重した幅広い業務に取り組まれている様子をご紹介。
親御さんのインタビューでは、事業所を決めるまでの経緯についても語っていただきます。
「多くの情報を得るために早い段階から行動」
障がいのある子どものひとり立ちを支える、親としての心構えも教えてくださいました。
◇「ダウン症のある青年の1日密着~ショートステイ編~」

ショートステイ編では、スタッフとの交流の様子、日中の事業所とはまた違った表情から、“暮らし”という視点で、家族以外の人と過ごすことの実際を紹介します。
将来、親から離れて自立できるのか?
家族以外の人と生活できるのか?
一人暮らしがいいのか、グループホームがあっているのか?
そんな、親御さんの将来への心配・不安に寄り添いたい、「集団での生活を通じて、次のステップへのチャレンジの場となる」ことを目指す事業所運営者さまのメッセージとあわせてご覧ください。 ◆「Special Learning」について
◆「Special Learning」について
社会福祉法人の職員様や、障がいのある方を積極的に雇用する一般企業の社員様を対象に、障がい者を支援するうえで必要となる知識をインターネット動画で学ぶことができるオンライン研修サービスです。
日常の支援でつまずいた時、自分がいま必要とする知識(コンテンツ)を自ら選択して学ぶ(視聴する)ことで、実際に適切な支援をおこなうことができるようにサポートします。
現在45都道府県1,400以上の事業所で導入いただき、約40,000人近くのユーザー数となります。